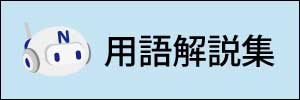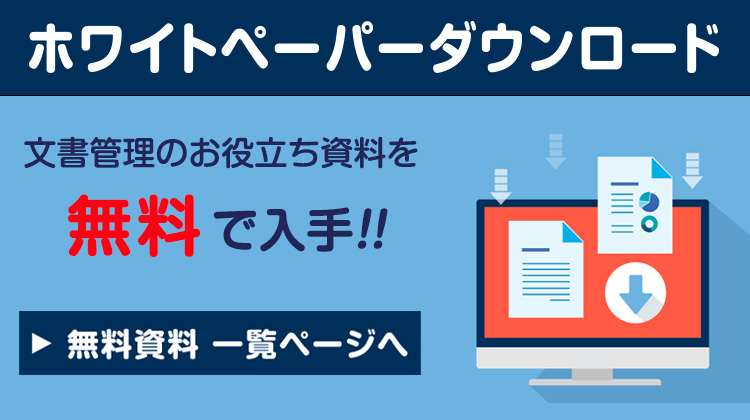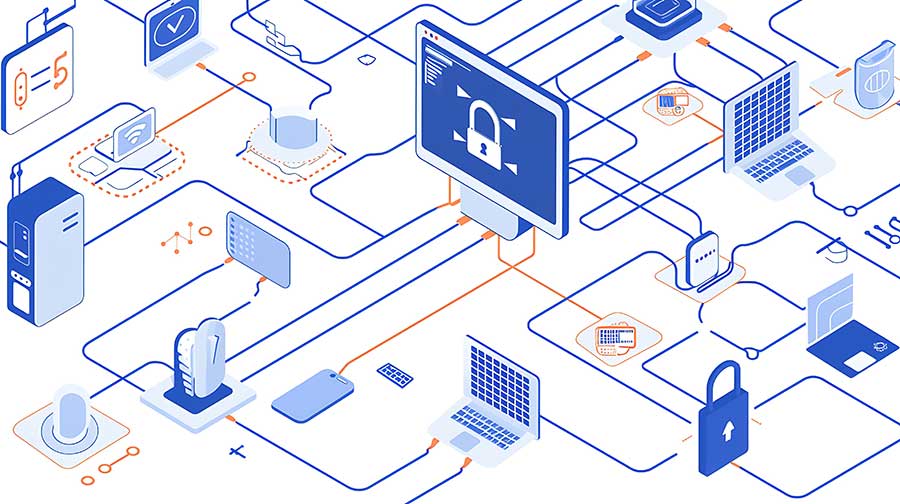アーカイブズの公開(利用)について詳しく解説します

アーカイブズは、原則として公開する責務がある資料です。
利用者はどのように求める資料を発見できるのか、アクセス可能性(Accessibility)と利用可能性(Availability)に注目して、詳しく解説します。
アーカイブズの公開とは
アーカイブズは単に歴史的価値のある資料を保存するのではなく、それらの資料を利用してもらうために存在します。よって、資料を利用可能な状態に保つことが重要です。このために考慮しなければならないことが、アクセス可能性(Accessibility)と利用可能性(Availability)です。
アクセス可能性とは、利用者が、求める文書・記録を発見でき、それに到達できるかどうかの可能性のことを言います。アクセス可能性に影響を与える要因としては、一般的に、目録などのツールの有無と正確性、所蔵機関の所在地(交通の便の良し悪し)と開館時間(利用できる時間帯や時間の長さ)などがあります。例えば、資料を発見(所蔵確認)できたとしても、所蔵機関が交通の便の悪い場所にあり、さらに開館時間が短ければ、アクセス可能な時間内に所蔵機関(及び資料)に辿り着くことは困難です。
一方、利用可能性とは、利用者が求める文書・記録を利用できるかどうかの可能性のことを言います。利用可能性に影響を与える要因としては、一般的に、利用状態(他の利用者が利用中か否か)、配架状態(正しく配架されているかどうか)などがあります。配架の誤りは利用可能性を下げ、同一資料の複数所蔵は利用可能性を上げます。
アクセス可能性と利用可能性がともに保証されることによって、資料の利用が可能となるのです。図書館や博物館と同様に蓄積・検索系の情報サービス機関であるアーカイブズでは、アクセス可能性と利用可能性を高めることが、サービスを提供する上での基本となります。アーカイブズの公開(利用)に関して、上記のアクセス可能性や利用可能性の観点から具体的に考えてみます。
まず、アクセス可能性を保証するツールとして、目録が提供されています。利用者の要求は様々です。利用者は、特定の資料(例えば「公文書管理の在り方に関する調査報告書」という特定の資料)を求めるかもしれませんし、特定の主題を持った資料(例えば“公文書管理”という主題を持った資料)を求めるかもしれません。また、要求が同じであっても、利用者の事前の知識には程度の差があります。
例えば、ある特定の資料を求めている場合、その資料のタイトルを知っている利用者とそうではない利用者では、求める資料へのアクセスの方法(経路)が異なってきます。いずれの利用者に対しても、アーカイブズはアクセス可能性を保証しなければなりません。そのためには、アーカイブズは利用者の要求を的確にとらえなければならず、目録の整備に加えて、利用者に対するレファレンス業務も重要となります。
一方、利用可能性に関して、アーカイブズにおいては特に、完全性や可読性を保証することが必要です。また、近年では文書・記録をデジタル化(デジタルアーカイブ)することも多く、これによって貴重な資料の閲覧、複数人での利用、遠隔地からの利用が可能となります。遠隔地からの利用は、アクセス可能性の向上にもつながります。さらに、展示や出版などによって利用を促進する(利用可能性を高める)ことも重要な任務です。公文書管理法には、「展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない」とあります(第23条)。
なお、紛失や配架間違いによって利用可能性が下がらぬように、利用者が直接資料(保存場所)にアクセスするのではなく、専門の職員が、資料と利用者を仲介するようにします。また、資料がファイルやボックス単位で管理されている場合は、利用者にこの単位で利用してもらいます。
まとめ
本記事では、アーカイブズの公開(利用)にあたっての、アクセス可能性(Accessibility)と利用可能性(Availability)ついて詳しく説明しました。
どんなに価値のある資料も利用されなければ意味がありません。利用可能な状態を保ち、アクセスしやすい環境を整えることが大切です。
日本レコードマネジメントでは、電子文書管理の専門知識と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合った電子文書管理の体制を構築、提供いたします。お気軽にお問い合わせください。