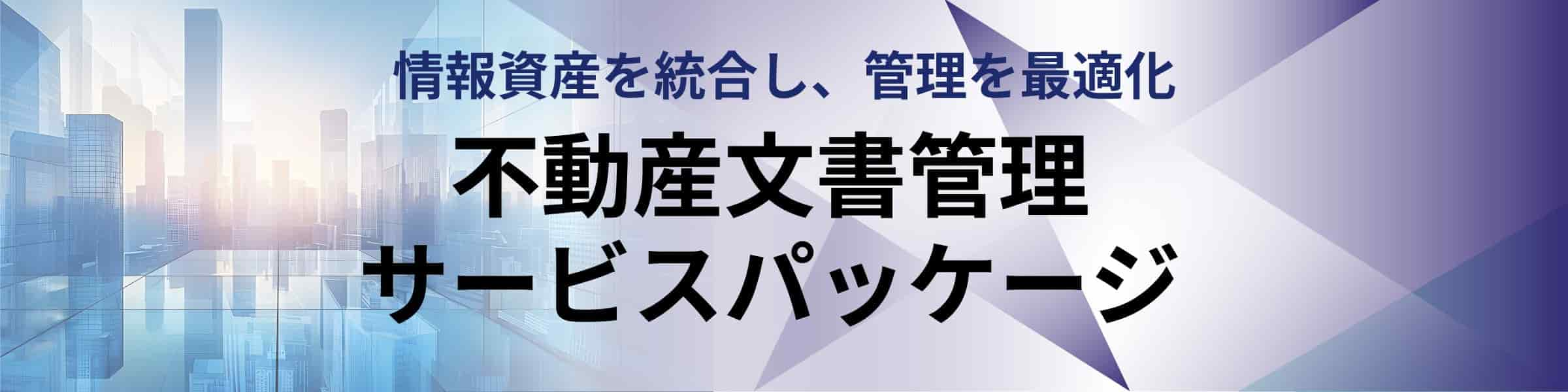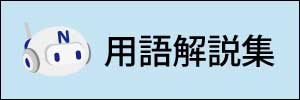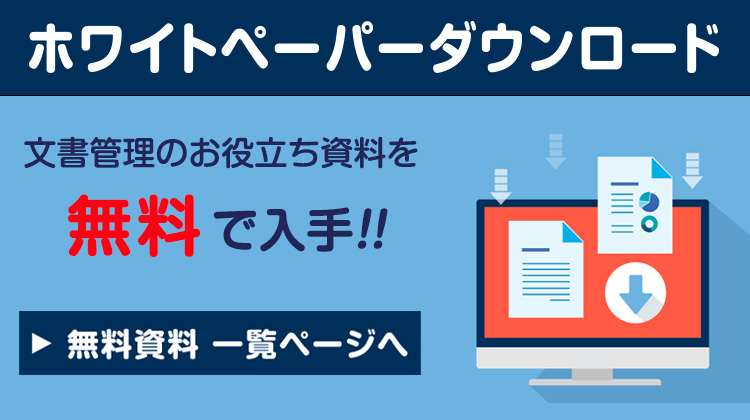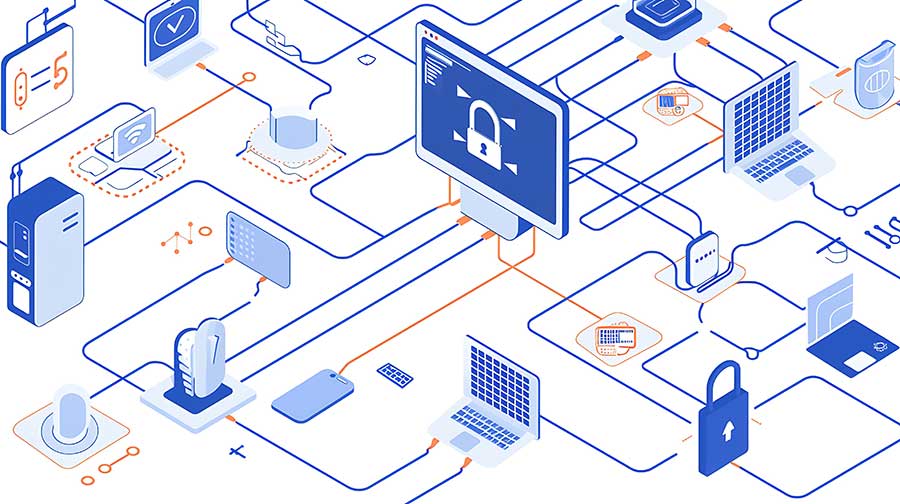事業を止めないために!企業が押さえるべき実践ポイントと注意点

BCPを整備しておけば、予期せぬ事態でも事業活動を早期に再開し、影響を最小限に抑えることができます。
企業が準備しておくべきBCP対策とは?
具体的にどのような準備を整えておくべきなのでしょうか。
ここでは、企業が実践すべきBCP対策のポイントをわかりやすく解説していきます。
ビジネスインパクト分析(BIA)
BIAとは、事業における重要な機能やプロセスを洗い出し、それらが中断した場合に生じる損失や影響を事前に評価するものです。
これは事業継続計画をつくるうえで欠かせない基盤であり、情報を細かく整理すればするほど、正確で実効性の高い分析が可能になります。
あらかじめ損失や影響を把握しておくことで、事業を継続するために必要な具体的な対策や優先順位を明確にできるのです。
リスクアセスメント
リスクアセスメントでは、まず潜在的なリスクを洗い出し、そのリスクが事業に与える影響を評価します。
手順としては、
- リスク要因をリストアップ
自然災害、システム障害、人的ミス、サプライチェーンの途絶などを幅広く想定します。 - 影響度を評価
各リスクが発生した場合に、事業活動にどの程度の打撃を与えるかを数値やランクで整理します。 - 優先順位を決定
影響が大きいリスクから順に対策を検討することで、効率的に対応できます。
このように事前にリスクを想定・評価しておくことで、企業が受けるダメージを正確に把握し、効果的なBCP対策につなげることができます。
対策と計画の立案
リスク評価やビジネスインパクト分析の結果をもとに、事業を継続するための具体的な対策を整理・計画します。
進め方のステップは以下の通りです。
- 代替手段の確保
- 代替オフィスやリモートワーク環境を準備しておく
- 主要設備やサーバーのバックアップ先を確保する
- 情報資産の保護と復旧体制
- クラウドや外部データセンターを活用したデータバックアップ
- サイバー攻撃や情報漏えいに備えたセキュリティ対策
- 通信・連絡手段の整備
- 緊急時に使える複数の通信手段(固定電話、モバイル、チャットツール等)を準備
- 顧客や取引先への連絡網を事前に整えておく
- 従業員の安全対策
- 避難計画、安否確認システムの導入
- 在宅勤務やシフト調整を想定した柔軟な働き方のルール整備
- サプライチェーン対策
- 主要サプライヤーのリスクを確認し、代替ルートを確保
- 在庫や物流の緊急時運用フローを用意する
計画を立てる際は、「理想的」ではなく 現実的に実行可能かどうか を重視してください。紙の計画にとどめず、実際に運用できるレベルまで落とし込むことが、BCPの成否を分けます。
緊急対応組織の整備
緊急時に迅速かつ的確な対応を行うためには、事前に専用の対応組織を整えておくことが重要です。
実務での準備ステップは以下の通りです。
- 緊急事態対応チームの設置
- 経営層、部門責任者、現場担当者などを含めたチームを組織する
- 緊急時の指揮系統を明確にする
- 役割と責任の明確化
- 意思決定、対外連絡、従業員の安全管理、システム復旧などの役割を割り振る
- 代替要員も事前に決めておく
- コマンドセンターの準備
- 緊急時の拠点(本社・サテライトオフィス・オンライン環境)を決めておく
- 必要な通信機器・電源・ネットワークを確保する
- 情報共有の仕組み構築
- 緊急連絡網、安否確認システム、チャットツールなどを用意する
- 状況報告と意思決定の流れをルール化する
この体制を事前に整えることで、緊急時にも混乱を避け、スムーズな指揮命令と復旧活動につなげることができます。
トレーニングと演習
BCPは「作って終わり」ではなく、定期的なトレーニングとテストを通じて検証・改善していくことが不可欠です。
実務での進め方は以下の通りです。
- トレーニングの実施
- 従業員に対し、緊急時の役割・責任、対応手順、連絡方法を周知
- 新入社員や異動者にも定期的に教育を行う
- シミュレーション演習
- 災害、システム障害、サプライチェーン停止などを想定したケース演習を実施
- 実際に避難や復旧作業をシミュレーションし、現場での対応力を高める
- 定期的なテスト
- 安否確認システムや緊急連絡網が機能するかをチェック
- データバックアップや復旧手順が計画通り動くかを検証
- 結果の振り返りと改善
- 演習やテストの結果を記録し、問題点や改善点を明確化
- 次回の計画や手順に反映し、BCPを進化させる
このサイクルを繰り返すことで、緊急時でも従業員が迷わず行動でき、計画の実効性を常に高めることができます。
監視と継続的な改善
BCPは、一度策定して終わりではなく、常に状況に応じて見直し・改善を繰り返す必要があります。計画が現実に即しているかを監視し、変化に対応できるようにしておきましょう。
実務での進め方は以下の通りです。
- 定期的なレビュー
- 年に1回以上、BCP全体を点検し、古い情報や不備がないかを確認する
- 事業内容や組織体制の変更があった場合はその都度更新する
- リスク環境の見直し
- 新たな自然災害リスク、サイバー攻撃、社会情勢の変化などを定期的にチェック
- 新しい脅威が見つかれば、計画に追加・修正する
- 実際の対応から学ぶ
- 災害やトラブルが発生した際は、対応内容を振り返り「何が有効だったか」「改善すべき点は何か」を整理する
- その教訓を次のBCPに反映する
- 改善策の反映と共有
- 更新した計画は必ず全従業員に周知する
- 関係部署や取引先にも必要に応じて情報を共有する
このサイクルを繰り返すことで、BCPは“使える計画”として成長し、企業の対応力を高め続けることができます。
環境や事業内容の変化に応じてBCPを見直し、常に最新の状態にアップデートしていく必要があります。実際の災害対応で得た教訓も反映しましょう。
BCP対策を行う際の注意点

事業を継続するためにBCP対策は欠かせませんが、ただ計画を立てればよいというものではありません。実効性を高めるためには、実施段階でいくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、BCPを運用する際に特に意識しておきたい注意点を整理して解説します。
リスク評価の網羅性
リスクアセスメントを行う際は、特定の分野に偏らず、できる限り幅広いリスクを洗い出すことが重要です。
チェックすべきリスクの例
- 自然災害
地震・台風・洪水・停電など - 技術的トラブル
システム障害、サイバー攻撃、通信不良 - 人的要因
人材の退職、ヒューマンエラー、労務トラブル - サプライチェーンの問題
部品供給の停止、物流の寸断、取引先の経営リスク
想定できるリスクを事前に網羅しておくことで、不測の事態が発生した際にも迅速に対応できます。逆に、想定外のリスクが抜け落ちていると、緊急時の対応が遅れ、被害が拡大する恐れがあります。
適切な対策の優先順位付け
対策をすべて一度に実行するのは現実的ではありません。そのため、事前に「何を優先すべきか」を決めておくことが大切です。
進め方のポイントは以下の通りです。
- BIA(ビジネスインパクト分析)の活用
- 事業に大きな影響を与える機能やプロセスを特定する
- 中断した場合の損失を数値化・可視化する
- 優先度を設定する
- 「最優先で守る業務」「短期間で復旧すべき業務」「後回しでもよい業務」に分類する
- 限られた人員・資金・設備を効果的に配分できるように整理する
- 柔軟に見直す
- 計画通りに実施できない場合もあるため、状況に応じて優先順位を見直せる体制を整える
このように、重要な業務にリソースを集中させることで、事業継続の確実性を高めることができます。
コミュニケーションの重要性
緊急時に最も混乱を招くのは「情報不足」や「誤った情報」です。だからこそ、正確かつ迅速に情報を伝える仕組みをあらかじめ整えておくことが欠かせません。
準備のポイントは以下の通りです。
- コミュニケーションプランの策定
- 誰が、どのタイミングで、どの情報を発信するかを決めておく
- 経営層から現場まで、情報の流れを明確にする
- 複数の連絡手段を確保
- 電話、メール、チャットツール、安否確認システムなどを組み合わせて活用する
- 一つの手段が使えなくても、別の手段で補えるようにしておく
- 情報の透明性と信頼性の確保
- 事実と推測を分けて伝える
- 社内外の関係者に同じ情報を共有し、誤解や不信感を防ぐ
このように、平時から計画と仕組みを整えておくことで、緊急時でもスムーズかつ信頼性のある情報共有が可能になります。
定期的なトレーニングとテスト
BCPは策定しただけでは機能しません。定期的なトレーニングやテストを実施し、従業員が実際に動ける状態を維持することが大切です。
実務でのポイントは以下の通りです。
- 従業員向けトレーニング
- 緊急時の役割や行動手順を繰り返し周知する
- 新人や異動者にも必ず教育を実施する
- シミュレーションや演習の実施
- 災害やシステム障害を想定したシナリオを用意し、実際に動いて検証する
- 訓練を通じて不足点や混乱ポイントを洗い出す
- 改善点の特定と反映
- 演習後は必ず振り返りを行い、問題点を整理する
- 改善点を次回の計画やマニュアルに反映させる
このサイクルを定期的に繰り返すことで、従業員の対応力を高め、緊急時に素早く行動に移せる組織体制をつくることができます。
継続的な改善と見直し
BCPは一度つくって終わりではなく、常に最新の状況に合わせて改善していく必要があります。組織や環境の変化に対応できるよう、定期的な見直しを欠かさないことが重要です。
実務での進め方は以下の通りです。
- 定期的な更新
- 年1回以上のレビューを実施し、古い情報や実現不可能な手順を修正する
- 組織改編や新規事業などがあれば、その都度計画を更新する
- 新たなリスクへの対応
- サイバー攻撃、感染症、地政学リスクなど、新しい脅威を定期的にチェックする
- 想定に加えていないリスクが見つかればすぐに計画へ反映する
- 実際の災害・トラブルから学ぶ
- 緊急事態対応の際に出た課題や改善点を記録する
- 教訓を次のBCPに反映し、実効性を高める
この継続的な改善サイクルを回すことで、BCPは“形だけの計画”ではなく、実際に使える仕組みとして成長していきます。
パートナーシップと連携
緊急時の対応力を高めるには、自社だけでなく外部との協力体制を事前に整えておくことが欠かせません。
実務での準備ポイントは以下の通りです。
- 関係先との連携強化
- 主要サプライヤー、顧客、物流業者、地域自治体などと協力関係を築く
- 緊急時に必要な連絡先リストを整理しておく
- 情報共有の仕組みづくり
- 災害やトラブル発生時に迅速に情報を交換できる体制を整える
- メール、チャットツール、専用ホットラインなど複数手段を用意する
- 共同での演習・確認
- 取引先や関係機関と合同でシミュレーションを行い、連携が機能するかを確認する
- 演習を通じて役割分担や改善点を明確にする
こうした協力体制を平時から準備しておくことで、緊急時にも迅速かつ効果的に対応でき、事業への影響を最小限に抑えることが可能になります。
法的・規制要件の遵守
BCPを策定する際には、法令や規制の遵守が欠かせません。違反すれば事業停止や社会的信用の失墜につながる可能性があるため、計画段階から必ず確認しておく必要があります。
実務でのチェックポイントは以下の通りです。
- 業界特有の規制確認
- 金融、医療、製造などの業界ごとに定められたガイドラインや規制を確認する
- 監督官庁や業界団体が公開している最新情報を常にチェックする
- 地域ごとの要件対応
- 災害対策基本法や自治体の防災計画など、地域独自のルールを把握する
- 拠点ごとに必要な対応を明確化する
- 計画への反映
- 法令や規制を踏まえた手順をBCPに盛り込み、従業員に周知する
- 監査や点検に備えて記録を残しておく
このように、法的・規制要件を確実に押さえたBCPを策定することで、リスク低減だけでなく企業の信頼性向上にもつながります。
まとめ
災害や緊急時において、事業体制をいかに早く立て直し、業務を継続・再開できるかは、企業にとって大きな課題です。そのためにも、平時からBCP対策を整え、万が一に備えておくことが不可欠です。
しかし、実効性のあるBCPを実施するには、正しい知識とノウハウに基づいた計画と運用が求められます。
日本レコードマネジメント(株)では、企業の事業継続を支えるために バックアップオフィスの提供や文書電子化サービス、文書保存サービスを行っています。
BCP対策の体制構築に課題を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。
企業の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。
本記事は、当社広報室にて発信しています。