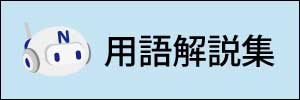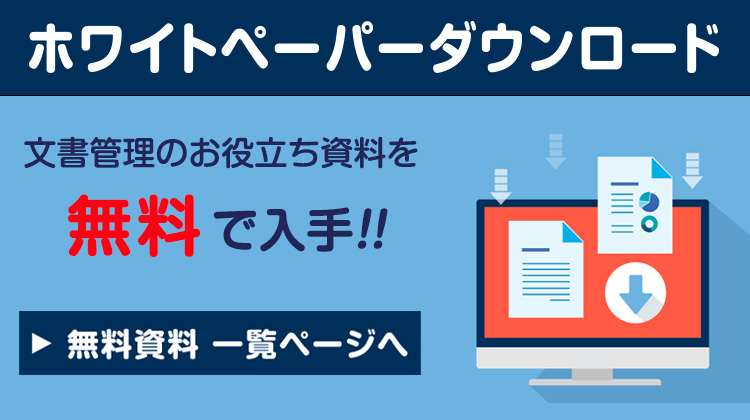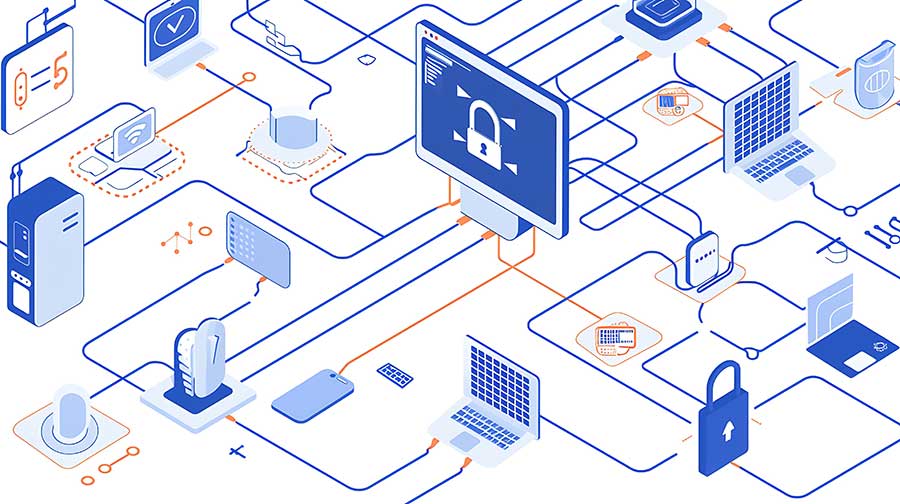紙の機密文書はどうやって廃棄する?わかりやすく解説!
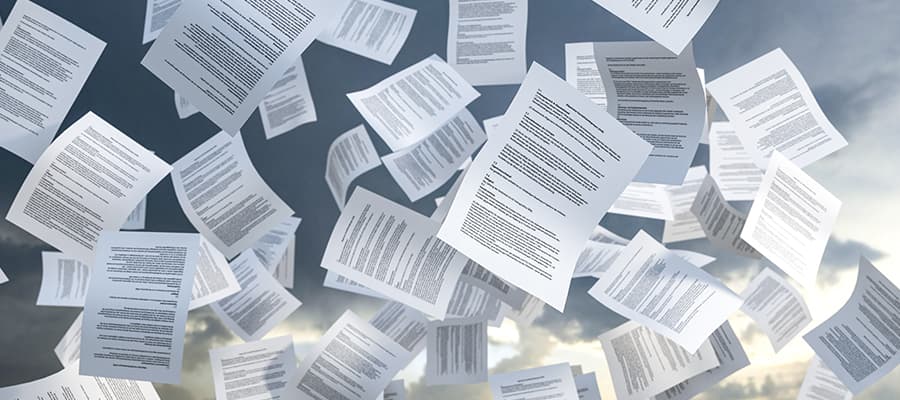
紙の機密文書を廃棄する時の課題や委託先について詳しく解説します。
大企業における機密文書の定義
大会社並びにその連結決算子会社においては、2006年5月に改正された会社法及び会社法施行規則の定めに従って、内部統制に係る基本方針を情報セキュリティ管理規程及び個人情報管理規程で示した上で、情報の取り扱いや分類を決定しています。
そのため、「意図を持って積極的または計画的に情報発信に努めるべき情報が記された文書や事業活動に関して一般に公開している文書以外は、機密文書である」と定義されます。大会社においてはその中身にかかわらず、情報が外部に流出すること自体が会社の信用を毀損することに繋がるため、作成した文書のうち公開文書以外は、全て機密文書とするのが一般的です。
機密文書の廃棄を取り巻く環境
「内的要素」は、機密文書を保持し排出する事業者である企業を指します。他方、「外的要素」は、その機密文書の廃棄を請け負う廃棄業者を指しますが、廃棄業者は現在も昔と変わらず、廃棄物(ゴミ)処理の延長で機密文書を機密古紙と偽って、原材料の量の拡大に奔走しており、排出事業者である企業に求められる内部統制やCSR経営の課題はもとより、それに関係する法令や条例も知らないというのが現実です。

新たに機密古紙という商品区分が生まれてはいるものの、その処理方法と定義は曖昧で、規制するルールが殆どないというのが実態です。その結果、廃棄業者の動きに歯止めが効かない上、企業側もコストの問題や危機感の欠如などで、機密文書の取り扱いに関する意識がなかなか高まらず、緩慢な管理体制のままとなっています。
機密文書の廃棄に関する課題
機密文書の廃棄に関しては、現状次のような課題が挙げられます。
管理レベルによる取り扱いの違い
機密文書は管理レベルによって取り扱いが異なりますが、規程などが整備されていないことが多いため、従業員全員が適正に廃棄しているとはいい切れない状況にあります。
組織の意識の格差
内部統制システムの整備が法的に義務化されている大手企業と、義務化されていない中小企業とでは、機密文書の廃棄に関して意識に格差があります。
機密文書の廃棄を受託する業者側の意識の格差
排出事業者である企業の法的要件が厳しくなっているにも関わらず、廃棄処分を請け負う事業者を規制するルールが緩いため、未だに廃棄物(ゴミ)処理と同じように取り扱われることが多々起こります。
機密文書の廃棄方法と委託先の選択
電子化や電子文書管理が進み、パソコンや企業の管理サーバーなどからの情報漏えいが頻繁にニュースで報道されますが、依然として紙媒体から流出する事故も少なくありません。また、一部の電子媒体の解読は専門技術が必要となりますが、我が国のように高い識字率を持つ国民は、小学生レベルでも、漢字、カナ、ひらがなを判読できるため、紙媒体の廃棄方法は重要です。
紙の機密文書の廃棄方法には様々な形態があります。機密文書廃棄の専門会社による専用廃棄施設における廃棄のほかに、オフィスでのシュレッダー裁断や自治体が管理しているごみ処理施設での焼却、製紙会社での直接溶解などがありますが、情報セキュリティや環境負荷、立地環境、安全面などの観点から、それぞれの廃棄方法には長所と短所があるため、文書量や機密度に応じた選択が必要です。
機密文書廃棄業者の選択において、「安全性」と「コスト」はトレードオフの関係にあります。安易にコスト削減ばかりを求めるのではなく、情報流出や漏えいによる企業の損害は、金銭面だけでなく、信用の毀損やブランドイメージの失墜などがあり、ダメージが非常に大きくなります。
委託先の事業者を選択する際は、廃棄施設の設備面の対策や企業の取得認証(プライバシーマークやISO9001、ISO14001など)は勿論のこと、記録情報管理士としての内部従事者に対する教育体制やそれに準じた資格取得など、専門人材の配置が今後は重要になってきます。
機密文書の廃棄と環境基本法
機密文書を廃棄する場合、情報流出の観点だけではなく、廃棄物(ごみ)の適正処理の観点からも処理方法を検討する必要があります。
廃棄物処理には、「環境基本法」を上位法とした「循環型社会形成推進基本法」に基づき、排出者責任 と 拡大生産者責任 を重要な理念とする、廃棄物を管理するための各法律があり、廃棄物の適正処理が求められています。廃棄物処理に関する法律としては「廃棄物及び清掃に関する法律」があり、「廃掃法」とも「廃棄物処理法」ともいわれています。また、3R(Reduce、Reuse、Recycle)に関する法律としては「資源有効利用促進法」があり、「リサイクル法」ともいわれています。
機密文書を廃棄する場合は、その業務を受託する廃棄物処理業者に限らず、排出事業者となる企業にも法律は適用されます。仮に、大手企業が、零細の廃棄物処理事業者に廃棄処理を委託し、情報の流出や漏えい事故が発生した場合は、信用の毀損など、排出事業者となる大手企業側が受けるダメージの方が大きいといえます。
機密文書管理における情報の流出や漏えいについては、損害賠償が発生することはすでに説明した通りですが、金銭的責任は、廃棄物の適正処理を怠った場合にも発生します。それは、前述の「廃棄物及び清掃に関する法律」にある罰則規定に定められており、1億円以下の罰金のほかにも5年以下の懲役などの刑罰が科せられます。
そのため、機密文書の管理においては、個人情報や営業秘密情報などの情報セキュリティ管理とともに、機密文書を廃棄物(ごみ)と認識した「廃棄物及び清掃に関する法律」の遵守が求められます。
廃棄物処理に関する法律の解説
循環型社会形成推進基本法
大量生産、大量消費、大量廃棄社会を資源循環型の社会に変えるために、国の基本的な考え方と国、事業者、国民の責務などを定めた基本法です。2000年5月に成立、2001年施行されました。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法などの個別法を束ねています。次の特徴を持ちます。
- 循環型社会の定義を明確に提示
- 法の対象となる物を有価無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、循環資源の再使用やリサイクルを促進
- 廃棄物処理やリサイクル推進における「排出者責任」と「拡大生産者責任」を明確に提示
- 廃棄物処理やリサイクルの優先順位を法定化(発生抑制(ごみを出さない)→再使用(リユース)→再生利用(リサイクル)→熱回収(サーマルリサイクル)→適正処分)
排出者責任
循環型社会形成推進基本法の第11条1項において、排出者責任として、廃棄物等の排出者が、自らの責任において、その排出した廃棄物等について、適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
拡大生産者責任
廃棄物処理問題が山積する中、生産者に製造物のリサイクルや廃棄処理に関しても責任を負わせることを指します。経済協力開発機構(OECD)が検討を重ねてきた考え方で、日本では、循環型社会形成推進基本法にその理念が盛り込まれました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
1971年(昭和46年)9月23日政令第三百号に施行され、2016年(平成28年)2月19日政令第四五号で、廃棄物の排出抑制と廃棄処理の適正化を行い、生活環境保全と公衆衛生向上を目的とした法律です。廃棄物の種類は様々あり、種類に対応した廃棄を行うことが義務化され、環境に与える影響を抑制する専門的な廃棄処理が求められることから、廃棄物処理業や廃棄物センターに関する法理的な拘束を行います。
まとめ
紙の機密文書の廃棄方法は様々な形態があります。コスト削減だけを追求すれば、安全性がおろそかになり、情報流出などの社会的な信頼を損なう結果になりかねません。また、廃棄物処理に関する様々な法律の遵守も求められています。紙の機密情報の適正廃棄が一筋縄ではいかないことがおわかりいただけたかと思います。
日本レコードマネジメントでは、安全・確実な機密文書の保管・廃棄サービスを行っています。お気軽にご相談ください。
本記事は、当社広報室にて発信しています。