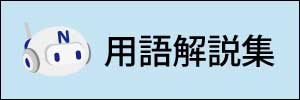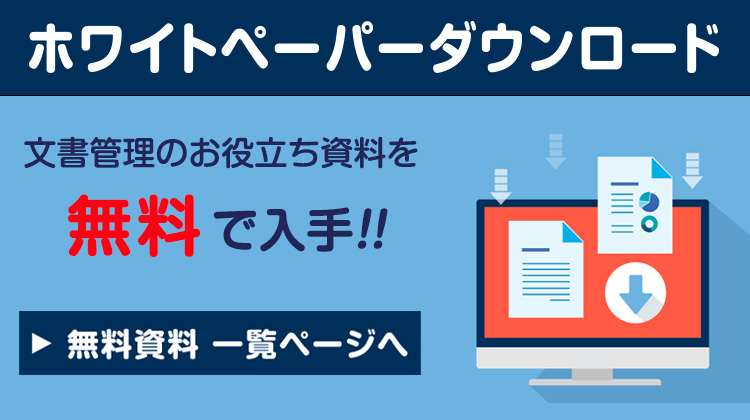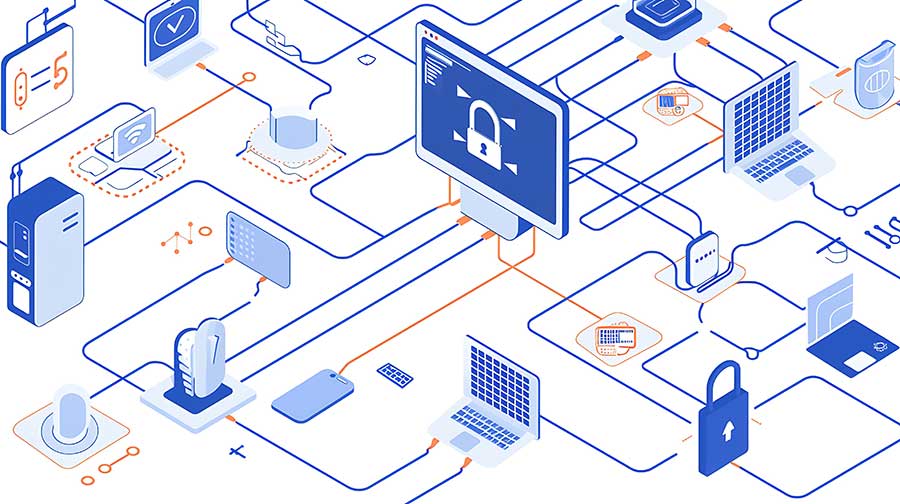特定歴史公文書等の利用方法と利用制限を解説

特定歴史公文書等への利用請求権
特定歴史公文書等とは、国立公文書館に移管された歴史公文書等のことを指します。公文書管理法には、主権者である国民から、公開した目録に基づいて特定歴史公文書等の利用請求があった場合には、利用制限事由に該当しない限り、国立公文書館等の長はそれを閲覧・利用させなければならないと定められています。
これは、国民の利用請求権と、それに対する国立公文書館等の義務を明確化したものといえます。これにより、情報公開法と合わせて、現用から非現用に至る公文書等の利用について、国民の権利が保証されることになりました。
ここで「公開」ではなく「利用」という文言が使われているのは、現用の行政文書を情報公開法により公開するのとは異なり、特定歴史公文書等は一般の利用に供することこそが本来の目的だからです。
国立公文書館等のアーカイブズ機関は、基本的に情報を公開し利用してもらうための施設です。そのため、特定歴史公文書等や、研究所その他の施設で保存されている歴史的、文化的または学術研究用の資料として特別な管理がされているものは、情報公開法の対象文書からは除外されています。なぜかというと、これらは情報公開法に基づいて公開請求する必要がないためです。
利用制限と30年ルール
全ての特定歴史公文書等が公開されるわけではなく、当該特定歴史公文書等に次のような情報が記録されている場合には、例外的に利用が制限されます。
- 個人情報
- 法人情報
- 外交防衛情報
- 犯罪捜査情報
- 事務・事業情報
- 監査・検査・取締り・試験等に関する情報
- 国または地方公共団体が経営する企業等に関する情報
これらの利用制限事由は情報公開法における「不開示情報」に該当しますが、本来特定歴史公文書等は利用を目的として保存されている文書なので、情報公開法における不開示情報より、その範囲が狭くなっています。例えば、不開示情報に含まれている「審議・検討情報」や「事務・事業情報」のうち“契約・交渉・争訟に関する情報”、“調査・研究に関する情報”、“人事管理に関する情報”は、特定歴史公文書等の利用制限から除外されています。
利用請求に係る特定歴史公文書等が利用制限に該当するか否かについて判断するにあたっては、利用請求のあった特定歴史公文書等の作成または取得からの時の経過を考慮すると同時に、移管元の機関からの意見を参酌しなければならないとしています。「時の経過を考慮する」とは、国際的に認められた「30年ルール」を踏まえることを意味しています。
「30年ルール」とは30年原則ともいい、1968年ICA(国際公文書館会議)マドリッド大会で採択された決議です。内容は、特定歴史公文書等が行政文書として作成または取得されてからの時の経過を考慮し、利用制限は原則として文書が作成または取得されてから30年を超えないものとするというものです。
利用制限事由から「審議・検討情報」及び「事務・事業情報」の一部が除外されているのは、これらは時の経過により利用制限の必要がなくなるという考え方によるものといえます。また、原本をそのまま閲覧させると破損や汚損のおそれがある場合も、利用に対する制限が認められます。
また、公文書管理法第21条には「利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる」とあります。利用制限に対しては、異議申立てをすることができます。
まとめ
特定歴史公文書等の利用と利用制限を解説しました。30年ルールについては、イギリスではさらに短い20年ルールを採用しており、日本も一部は20年ルールを適用しています。日本では公文書をめぐる問題も起きており、法律をはじめ体制の構築が課題となっています。今後の公文書管理の動向に注目しましょう。
日本レコードマネジメントでは、行政機関における公文書を始め、情報の整理・管理から発信に至るまで、最新の情報技術を活用したサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。