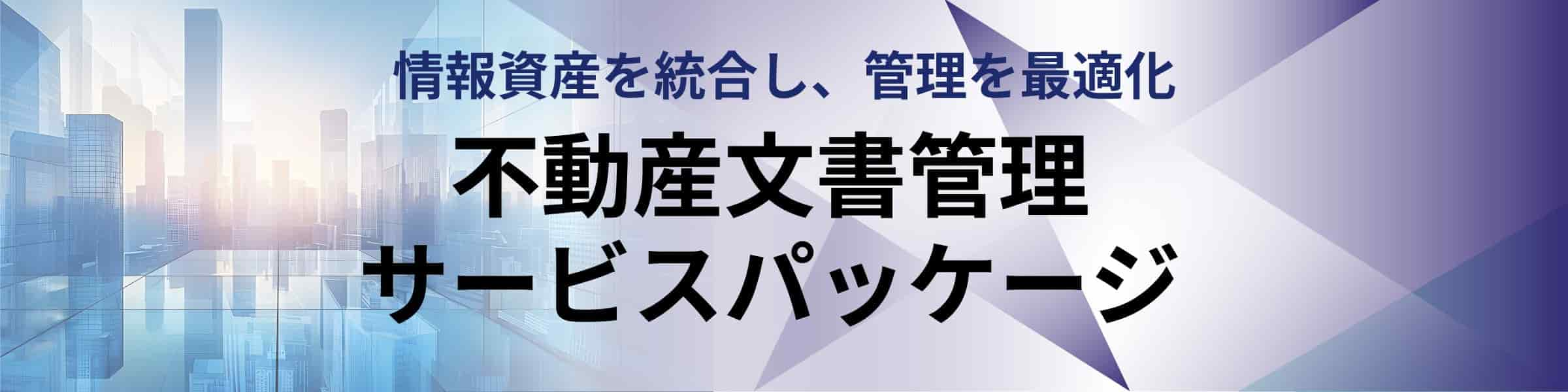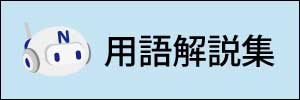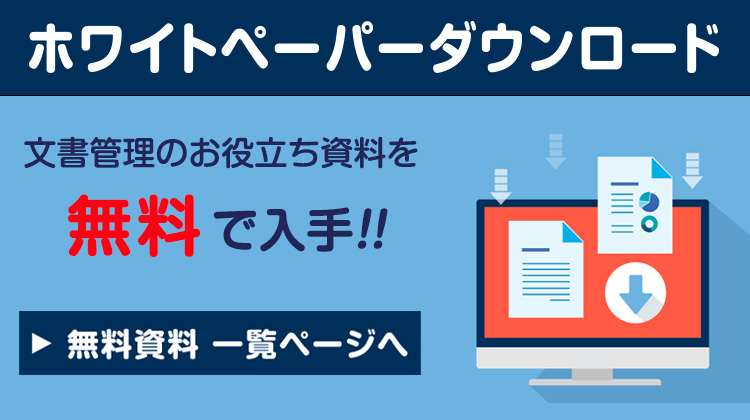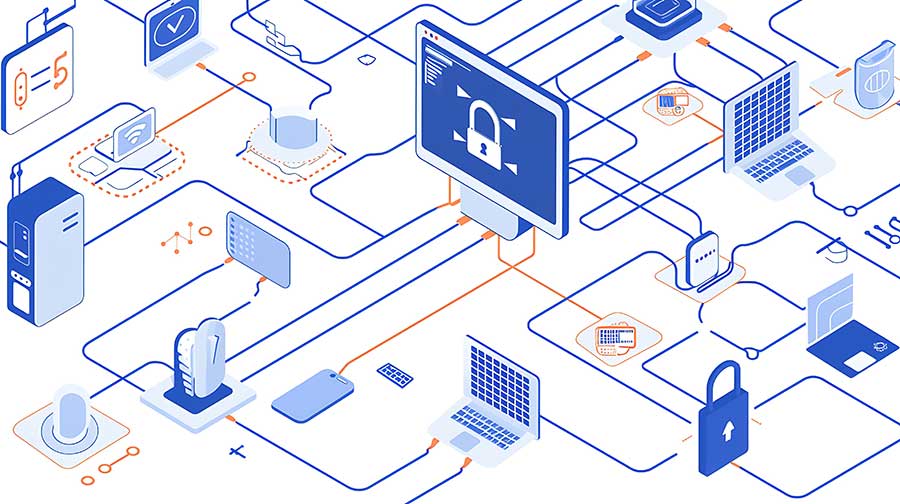電子商取引について詳しく解説します

電子商取引とは、インターネットなど通信ネットワークを利用して行われる取引を指します。
本記事では、電子商取引の法制度について詳しく解説していきます。
インターネット上の電子商取引
インターネットを通じた様々な情報のやり取りが進むにつれ、ネットワーク上での商取引である電子商取引(Electronic Commerce:EC)が急成長しています。成長要因としては、急速に普及するスマートフォンやタブレット端末などを利用して、商品の検索から決済までをネットワーク上で行えるようになったことが挙げられます。しかし、電子商取引は、商取引額全体でみると2019年時点では3割弱に過ぎず、インターネットで利用されているサービスとしてグローバルに広く普及しているものの、まだまだその成長の余地は十分に残されているといえるでしょう。
企業と一般消費者との間で行われる電子商取引はB to C(Business to Consumer)またはB2Cと呼ばれ、企業と企業の間で行われる電子商取引はB to B(Business to Business)またはB2Bと呼ばれます。B to Cでは、ホテルの予約、証券取引からパソコン・家電製品などの最終消費財やネットワークコンテンツなどのサービスまで、様々な取引が行われていますが、最近では書籍や衣料品など趣味関連雑貨のウエイトが増えています。B to Bでは、企業間における受発注、例えば原材料や部品の購買・調達などが中心となっています。
電子商取引促進のための基盤整備
国連「電子商取引のモデル法」(1996)(UNCITRAL:Model Law on Electronic Commerce)
1996年に制定された国連国際商取引法委員会の「電子商取引のモデル法」は、世界的に各国の電子商取引に関する法制度の確立に大きな影響を与えたもので、大変示唆に富んだ内容になっています。
このモデル法の目的はいうまでもなく、国際的な商取引の場において電子メールやEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)などの新しい通信手段の利用が急速に増えていること、及び情報ハイウェイやインターネットなどの情報技術の進展に鑑み、ペーパーレスメッセージの形式での重要情報のやり取りが妨げられるかも知れない法的な障害やそれらの法的効力についての不安を取り除くことにありました。
そして、世界各国の立法者に対し、電子商取引に関するより確実な法的環境を整備するための国際的なルールを提供することが意図されたのでした。以下、一般的な電子文書の管理にも参考になる重要な項目につき、関連条文を見てみることにしましょう。
データメッセージの法的承認
「情報は、それがデータメッセージの形式であるという理由で法的効力、正当性、実効性を否定されてはならない」(第5条)
データメッセージ、すなわち電子文書の法的効力は基本的に紙文書と同等でなければならないということを明確にした点で意義があります。電子商取引のみならず、訴訟における証拠能力にも関連する問題です。
書面
「法律が情報は書面でと要求している場合でも、その情報が後の参照利用に際し検索可能ならば、データメッセージはこの要求を満足する」(第6条)
電子文書の見読性の問題です。電子文書はもともとMachine readableであり、パソコンなどの画面に表示するか、紙にプリントアウトしない限り読めないという特性があります。従って、必要な電子文書が必要な時に何時でも検索でき、参照できる状況になっていないといけないのです。また、インデックスの完備など、検索の容易性も要求されます。
署名
「法律が個人の署名を要求している場合でも、その個人を識別でき、データメッセージに含まれている情報をその個人が承認していることを示す方法があるなら、データメッセージはこの要求を満足する。」(第7条)
電子文書の作成者と称している人間が本当にその文書を作成したかどうかを、どのようにして証明するかという問題です。これは電子文書の真正性の問題であり、これを解決する方策が、正に、電子署名なのです。
原本
「法律が、情報をオリジナルの形式で提出、又は保有されるよう要求する場合でも、情報がデータメッセージとして、最初に作成された時の形式のままであるという完全性につき信頼できる保証があるなら、データメッセージはこの要求を満足する」「完全性を評価する基準は、その情報が完成されており、変更されずに残っているかどうか、また通常の伝達、保存、閲覧の課程で何らかの追加・修正が加えられていないかどうかでなければならない」(第8条)
電子文書は追加、修正、削除などの変更が容易にできるというメリットがありますが、同時にこれは改ざんなどの不正な変更が跡形もなくできるという点でデメリットになります。従って、電子文書の完全性、つまり文書が完成しており、後で修正変更されていないかが重要であり、本条はそのための評価基準を明らかにしています。
電子メッセージの法的証拠能力
「いかなる訴訟手続においても、それがデータメッセージであるという理由だけで、データメッセージの法的証拠能力を否定するような証拠規則の適用は行われてはならない」「データメッセージ形式の情報にも正当な証拠としての重要性が与えられるべきである。データメッセージの証拠としての重要性を評価するには、そのデータメッセージの作成、保存、伝達の方法に関する信頼性、並びに情報の完全性維持の方法及び作成者を識別する方法に関する信頼性に対して、考慮が払われるべきである」(第9条)
訴訟における電子文書の証拠能力を基本的に認めており、その評価基準を明らかにしています。
データメッセージの保有
「法律がある文書、記録又は情報の保有を要求する場合に、データメッセージが次の条件を満たすならば、その要求は満足される。
- データメッセージに含まれる情報が後の参照利用に際し検索可能なこと
- そのデータメッセージが作成、送付、受領されたフォーマットで保有されているか、またはその情報が実際に再現、提示可能なフォーマットに保有されていること
- どのような情報であれ、そのデータメッセージの発信元、送付先、送受信の日時などが識別できるような方法で保有されていること」(第10条)
本条は電子文書の利用性、つまり後の参照利用のために必要な条件を明らかにしており、そのための文書の属性情報(メタデータ)の重要性を指摘しています。
以上、国連の「電子商取引のモデル法」から、単に電子商取引のみでなく、一般的な電子文書の管理にも共通する重要項目を拾い出してみましたが、参考になる点が多いと思われます。
国内各種法制度の見直し
インターネット上での電子商取引を促進し、それらが企業の取引活動の基盤として十分に機能するためには、従来のインターネット上の取引を前提にしていない各種法制度の見直しを行う必要がありました。
そこで政府は2000年11月に「IT書面一括法」*1)を成立させ、電子商取引の阻害要因の一つになっている書面の交付あるいは書面による手続きを義務付けている規制を改正、従来の手続きに加え、電子的手段によって行えるようにしました。具体的には、従来は契約などに際し取引条件などを記載した“紙”による書面の交付を義務付けていたものを、従来の書面による手続きに加え、顧客が同意した場合に限って、電子メールなどによっても行えるように制度を改正したのです。
その他、2001年1月には、インターネットなどの高度情報通信ネットワークを活用し、創造的で活力ある社会を実現するための基本的なインフラ整備を目的とした「IT基本法」*2)が、また同年4月には電子署名が手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤の確立を目的とした「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)が施行されています。
インターネットの活用により電子商取引が様々な分野で普及するようになってきましたが、一方では情報通信ネットワークの安全性・信頼性に対して不安を持つ利用者が増大しつつあり、これらを解消する必要性が出てきました。
ネットワーク上の情報セキュリティについては、「なりすまし」などの不正アクセス問題、コンピューターウイルスの問題など様々なリスクが指摘されていますが、最近特に脚光を浴びているのが個人情報保護に関する問題です。
中でも個人情報の漏えい問題は深刻な社会問題となっており、社会経済活動のネットワーク化に伴う今後の大きな課題の一つになっています。個人情報保護に関する法律としては、これまで「行政機関の保有する電子計算機に係る個人情報の保護に関する法律」(1988年施行)がありましたが、これは対象がコンピューター情報に限定されている上、民間の保有する個人情報が対象となっていないなどの問題がありました。そこで政府は本格的な個人情報保護法の制定に向けて検討を進め、2003年5月に「個人情報保護関係5法」を制定するに至ったのです。
*1)正式には「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」2001年4月施行
*2)正式には「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」2001年1月6日施行
まとめ
電子商取引について解説しました。インターネット上で、検索から決済まで行える便利な電子商取引ですが、不正アクセスやコンピュータウィルス、個人情報の漏洩など様々なリスクもあります。次回は、そんなインターネット上に潜むリスクについて詳しく解説します。
日本レコードマネジメントでは、電子文書管理の専門知識と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合った電子文書管理の体制を構築、提供いたします。お気軽にお問い合わせください。